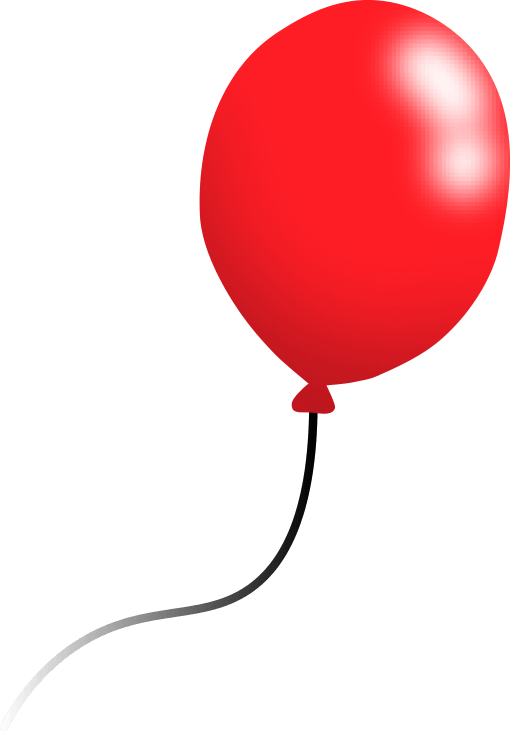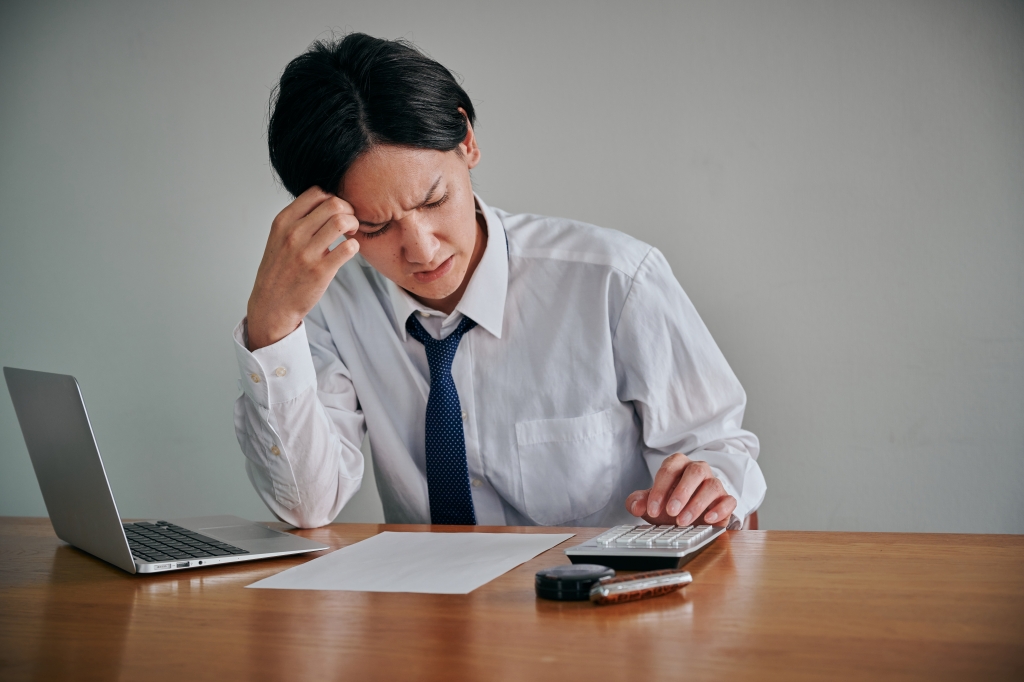食品製造と飲食店経営の2つの事業をしている会社があって、飲食店部門を切り離して、設立した新会社に移転する、もしくは既存の他の会社に移転させることを会社分割といいます。それは飲食店部門の全部でも良いし、数ある飲食店の内の一つの店舗に関するものでも良いのです。
分割した事業を新しく設立した会社に承継させる事を新設分割、既存の会社に承継させることを吸収分割と言います。
会社分割は対価を伴う点で(勿論、無対価型もあります。)、そして事業の一部を譲渡する点で、M&Aの一つである営業譲渡(事業譲渡)と類似します。
営業譲渡は、事業の売買であり、その対価は課税の対象となります。一方会社分割は組織法上の行為であり、一定の要件を満たせば非課税となることが特徴としてあげられます。
同じ組織法上の行為である合併と会社分割との差異は、合併は会社が消滅するのに対し、会社分割は消滅いたしません。また保証債務など簿外負債に関し、合併はあとでそれが発覚し問題となりますが、会社分割はその様な問題は基本的に発生いたしません。
ここで、会社分割して事業を承継させる会社を分割会社、事業の承継を受ける会社を 承継会社 と呼ぶ事にいたします。
会社分割にあたり、当該事業とそれに関連する債務が承継される場合が殆どと思われますが、債務者を分割会社から承継会に変更する場合、通常は債務引受という契約を承継会社と債権者との間で交わすのが原則です。しかし、会社分割においては必要ありません。債権者にたいし債権者保護手続きのみをすれば足りるのです。手続きとしては官報で会社分割をすることを公告し、知れたる債権者には別途通知いたします。異議の出た債権者には弁済、もしくは担保を供すこととなります。また、分割会社が債権者との間で重畳的債務引受をしておけば、債権者保護手続きは必要ありません。重畳的債務引受とは債務を負うのが、承継会社だけでなく、分割会社も負っていくという契約です。
承継会社に債務を承継させない場合、分割会社の債権者に対しては、債権者保護手続きすらも必要がありません。承継会社から移転した資産と等しい資産(承継会社の株式等)を対価として取得し、分割会社の資産に変動がないことを理由といたします。その結果、優良事業を承継会社に移転させ、不採算部門を残存させ、分割会社を破産や特別清算等で清算してしまうケースが多く見られ、昨今問題となっています。訴訟に発展した場合、信義則違反、法人格否認の法理でもって会社分割無効、また最近では、東京高裁(平成22年10月27日)において、会社分割行為が詐害行為取消の対象となる判決が出されています。かかる問題が頻出すれば、立法再考も考えられるところであります。